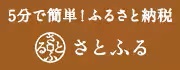生産のコダワリ
-

比較的冷涼地帯ということもあり、青森県の防除暦はもともと使用薬剤数は少なめに設定されておりますが、近年の温暖化による害虫の生態の変化と病原菌の耐性菌発生による全県を挙げての蔓延防止が必要となってきました。殺虫剤に関しては、基準の半分以下の使用数になるように散布設計しています。もちろん単なる減農薬が目的ではなく、一大産地を守る上で、農薬の使用が全くの悪者であるとは感じておりません。病害虫が蔓延するのを防ぎ、継続的に商品価値の高い生産物を産み出すことが最大の目的でありつつ、「無駄な薬剤を削減する」「ある程度の病害虫被害を許容する」「生態系のバランスの取れた’生きている’園地作り」目指して取り組んでおります。
マイナーな害虫には極力目を瞑っておりますので、従業員の方々には少しだけ我慢してもらっております。ただ、スズメバチ、アシナガバチが樹冠の中に巣作りしやすいのが玉に瑕です。専用の殺虫スプレーが欠かせません。 -

「ふじ」で実施する際は葉っぱの機能を最大限に使い尽くし、完熟させてからの収穫となります。
早生種や中生種の赤色品種で実施する際は、なかなか黄変落葉を待ってというわけにはいかず収穫のタイミングは難しくなりますが、葉を取らなくとも果実に光が当たるように管理しつつ、食味が十二分に乗ったのを確認してからの収穫となります。
そして、2023年からAT farmの葉とらずりんごは【はあとりんご】と称します!詳細は関連ページをご参照ください。クリックでジャンプ) -

-

-

-

-

収穫作業は非常に効率がいいのですが、作業空間が意外と狭く、大人数での作業は必ずしも効率的とは言い難いです。開園コストが高いのも難です。 -

園地における樹の栽植本数を多くして、単位面積当たりの収量を早く且つ多く上げるということ、省力化、機械作業を導入しやすくということが目的として挙げられますが、当社としては樹と樹の間隔は狭めつつも、作業効率のため列間は広めでとの考え方です。それぞれ一長一短はあるようです。
如何にして樹がコンパクトになり得るのか、「省力」して「小玉」で「美味」しい果実を早期に収穫して、産地としてお客様に対しても手に取りやすい価格実現を目指すべきとの考えから導入しております。
従来の栽培管理とは多少違った視点が必要です。ただ、日本の北国では梅雨期から初夏に限られた日照時間となる傾向があるため、翌年の花芽形成に不利とされております。
とにもかくにも毎年、継続して成りこませることが最も大事になっていきますので、もうしばらく試験栽培が続きそうです。